キャラクターの話し言葉が、ジェンダー・ギャップを助長する?「役割語」に見る、日本社会の性格差問題。
低成長・低投資・デフレから抜け出せず、「失われた30年」と揶揄されて久しい日本経済。しかし、停滞を続ける日本の産業の中でも、堅調に伸び続けている分野がある。それが、キャラクタービジネスだ。経済産業省の発表によると、アニメや漫画、ゲームを筆頭とした日本のコンテンツ産業は、この10年間で約3倍に成長。海外売上は2023年時点で約5.8兆円に上っており、これは同年の半導体産業の輸出額を超え、自動車産業に次ぐ規模である。同産業を日本経済の柱にしようと、政府はコンテンツ産業の海外売上20兆円をめざす5ヵ年計画も策定。ゲームやアニメの海外展開を加速させる100のアクションプランを発表している1。
今回はキャラクターやキャラクター産業が社会に与えている影響を紐解くべく、フィクションにおける「役割語」を研究する大阪大学名誉教授・金水敏先生を訪問。役割語という観点からキャラクター産業を眺めると、豊かな文化であるはずのアニメや漫画の背後に、性役割のステレオタイプ化やジェンダー・ギャップの助長といった、日本社会が抱える課題点が見えてきた。
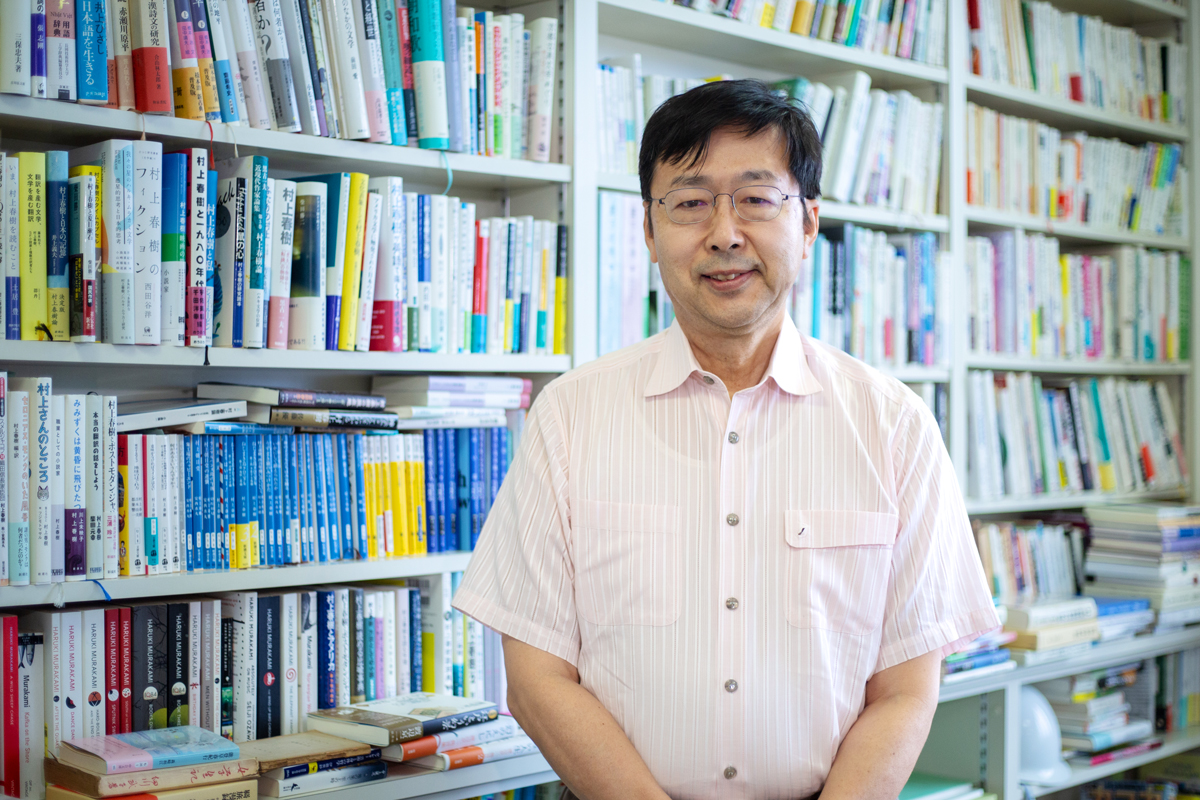
知らず知らずのうちに、「役割語」の影響下にある私たち。
テレビはもちろん広告、グッズ、イベントなど、生活の至る所に溢れかえるキャラクターの存在。年齢や性別を問わず、キャラクターに触れずに生活する方が難しいと言えるだろう。とはいえ多くの人々にとって、まだまだアニメやゲーム、漫画は個々人が好みに合わせて適度に楽しむ文化。「オタク」と呼ばれるようなディープなファン以外、生活や人格に大きく変化を与える影響を受けることはない、と思っている人がほとんどのはずだ。
しかし、本当にそうだろうか?大衆化されたキャラクターから、大衆である我々は影響を受けていないと言いきれるだろうか?そんな疑問にひとつの答えを出してくれるのが、金水教授が研究テーマとする「役割語」という概念だ。
役割語とはアニメや漫画において、キャラクターの年齢や性別、属性を定義する話し方、独特の言葉遣いのこと。具体的には老人や博士といった高齢で知的なキャラクターが話す「わしは〇〇しておる」「そうなのじゃ」や、お嬢様キャラが話す「〇〇ですわ」「よくってよ」といった話し方などが、それにあたる。
金水教授がこの概念を見出すきっかけとなったのは、博士論文の研究過程で得たひとつの気づきだ。「元々は、いる/ある/おるという日本語の使い分けについて、歴史や方言の観点から研究を行っていました。“ある”は無生物に用いられ、“いる”・“おる”は生物に共通して用いられる。西日本では(人が)おる、と言うのに対し、東日本では(人が)いると言うなど、地域、方言によって用法が対立している……といった観点の研究です。その時気づいたのが、歳をとった博士や魔法使いなどのキャラクターが“わしはここにおる”という言葉遣いをすること。歴史的変化でもなく、方言でもないのに“おる”が使用されている。この用法を説明するべく、行き着いたのが役割語という概念です」と金水教授は語る。
2000年、教授は役割語に関する論文を発表し、2003年には『ヴァーチャル日本語 役割語の謎(岩波書店)』も刊行。現実世界では誰も使わない言葉、フィクションの中でのみ登場する話し方であるにもかかわらず、日本人なら誰しもその意味するところや描こうとするキャラクター性を理解できる。当たり前すぎて誰も気づいていなかった不可思議さや、知らず知らずに自分たちが影響を受けている概念の発見が話題を呼び、役割語は多くの人が興味を抱くトピックスとなっている。
我々がどの程度役割語の影響下にあるのか、少しテストをしてみよう。白衣を着て、白髪を生やした博士のキャラクターが、2人並んで立っているところを想像してみてほしい。2人は全く同じ見た目、同じ声だが、右のキャラクターは「僕はここにいるよ」と話し、左のキャラクターは「わしはここにおるぞ」と話す。普段からアニメや漫画に積極的に触れているかどうかに関わらず、ほとんどの人が、右の博士の話し方に大きな違和感を感じ、左の博士の話し方がしっくりくる、と感じるのではないだろうか。
このことから分かるのは、我々の中にある役割語に対する感覚の根深さ。少なくとも役割語という観点において、私たちのほとんどはキャラクター文化による大きな影響を受けているということが分かる。
日本の役割語は、自由度、柔軟さにおいて唯一無二。
「ここまで役割語が豊かに広がっていて、大衆に根付いているのは日本語ならでは」と金水教授。性別や年齢を定義するような話し方だけでなく、「〇〇なのニャ」といえば猫、「〇〇だワン」と言えば犬といった形で、特定の語尾を付与するだけでそのキャラクターに人間以外の役割も付与できることを思うと、確かに選択肢は無限大だ。
ただ、役割語という概念が日本だけのもの、という訳ではない。英語にも役割語と言える言葉が存在しており、African-American English Vernacular、通称“AAEV”と呼ばれる黒人英語や、イギリスの方言のひとつであるコックニーなどがそれにあたる。映画などでは、こういった方言、訛りがキャラクターの特性や生まれを表現するために用いられる場面も多い。
しかし英語の役割語は、人種や地域性を感じさせる方言、訛りといった枠を出ることはないため、日本の役割語とは異なる特性を持つのだという。「端的に言うと、日本語の役割語は足し算で、英語の役割語は引き算」と教授は言う。「ニャ」や「ワン」といったキャラクター性を足して役割を与える日本語に対し、訛りや方言のある英語は文法や発音が抜けたり崩れたりした非正規的なもの、と捉えられている。つまり上流階級が話す「問題のない正しい英語」に対して、なんらかの引き算が発生した言葉、「何かが足りていない英語」として扱われているのだ。
「引き算たる英語の役割語が使用されるのは、恵まれない境遇や貧しさなどを付与してそのキャラクターの地位を低く見せる時に限られます。一方で日本語の役割語の中にはむしろ、王や支配者などキャラクターの地位を高めるために使われるものも。英語より幅広い役割の定義が可能で、自由自在に変化させられるからこそ、ストーリー性やエンタメ性を豊かにする装置として重宝されているのだと思います」と金水教授は語る。
役割語の再生産が、ジェンダー・ギャップを助長する可能性も。
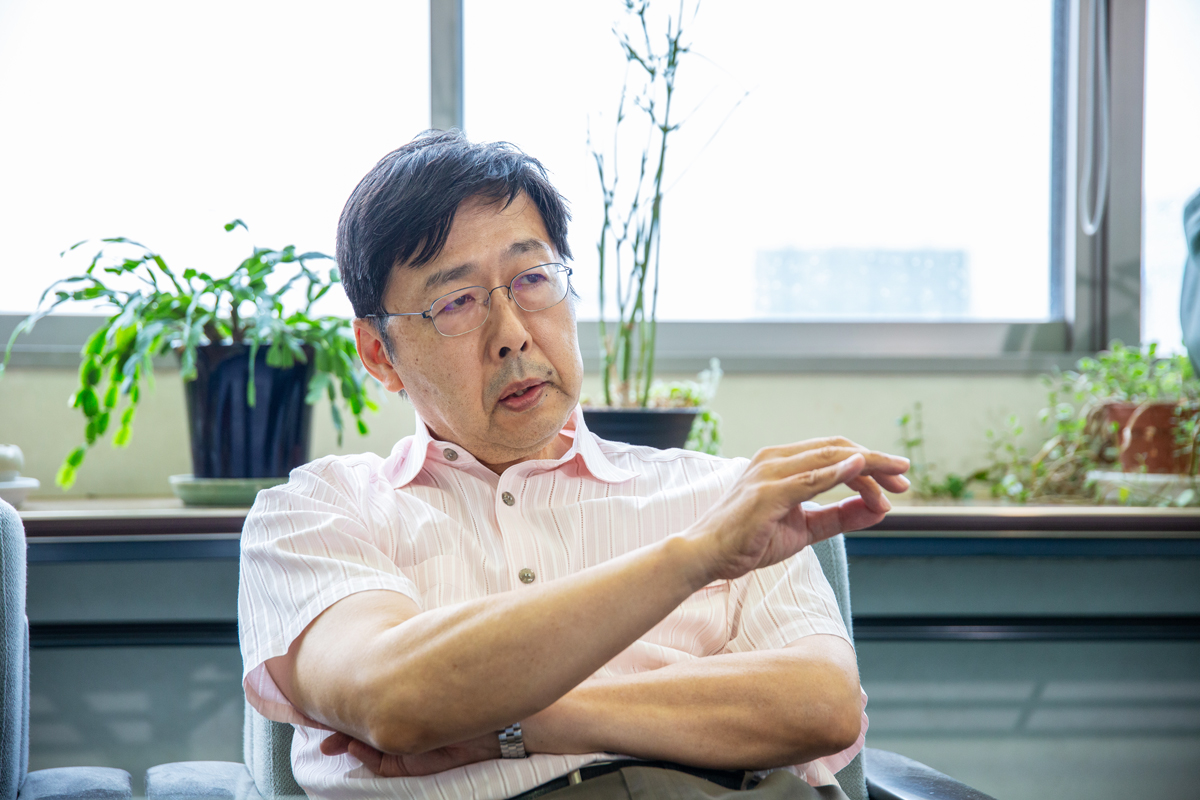
日本独特のものとして育ってきた役割語が、世界に誇る日本のキャラクター文化を支える要因となっていることは間違いなさそうだ。ただ一方で、役割語が日本社会に好ましくない影響を与えている可能性も否定できない、と金水教授は言う。「“〇〇なのじゃ”などと、博士のように話す人は現実世界にそうそういないため、特に問題になることはないでしょう。ただ、役割語が持つ男性キャラクター、女性キャラクターをはっきりと区別するという機能は、実社会にマイナスな影響を与えている可能性が非常に大きい。私は役割語による性区別が、日本のジェンダー・ギャップを助長する要因になっているのではないかと推察しています」。
ジェンダー・ギャップとは、経済活動や政治への参画度、教育水準などに関して、男女の違いによって生まれる格差を示す指標。内閣府の発表によると、2025年時点で日本のジェンダーギャップ指数は148ヶ国中118位2であり、これは先進国の中では最低レベルの位置付けだ。先進的な社会構造を有しているにも関わらず、埋まることのない日本のジェンダー・ギャップ。その原因のひとつが、コミュニケーションの礎となる「話し言葉」に、根深い性区別が存在しているからなのではないか、というのが金水教授の見立てだ。「最も象徴的なのは、女性の役割語に“命令形”がないという事実」と教授は続け、ビジネスの現場での会話を例に、この問題点を説明してくれた。
上司と部下が話しているとする。部下には心配事があって、それを上司に相談しているような場面だ。男性上司がその話を聞いて「心配するな!」「頑張れよ」と、部下を鼓舞する言葉を返す。この一連のシーンに、違和感を感じる人は少ないだろう。では、上司が女性だった場合はどうだろうか?女性の上司が「心配するな!」「頑張れよ!」と部下を鼓舞する。男性上司と同じセリフなのに、大きな違和感が生まれると同時に、女性上司が非常に高圧的な人間に見えてくる。
「こういったシーンを想像することで “心配するな” “頑張れよ”という命令形の言葉を、女性は話すことができないという事実がよく分かります。女性上司が“心配しないで”“頑張って”と言えば、違和感がなくなると思いませんか? つまり、女性は命令ではなく“お願い”をすることを期待されており、それに則った役割語を社会から与えられてしまっているんです」。このように使われている言葉を細やかに紐解き、男女で並べてみると、役割語がフィクションの世界から染み出して、実世界でも機能してしまっていることがよく分かる。しかし日常生活の中で言葉による性区別に気づいたり、是正したりすることが難しいのも事実だ。「やはりそれは、幼い頃から触れてきているアニメなどによって、私たちの中に性別によって異なる役割語が深くインプットされているから。アンパンマンやスタジオジブリ作品など、子どもたちが大好きな作品は役割語に溢れています。そうやって世代を超えて役割語は伝播し、そこに付与されている性区別も再生産されているのです」と金水教授は話す。
女性自称詞の多様化は、
非対称性の治癒に向けた変化の兆し?
命令形の有無に並んで、男性女性で大きな非対称性が見られる言葉が、自分を指し示す際に使う「自称詞」だ。俺、僕、私、おいら、わし……など男性が使える自称詞が数限りなくある一方で、女性が使える自称詞は「私」か「あたし」程度。男性がくつろいでいる時や近しい間柄の相手に対して使う「俺」「僕」に当たる言葉が無く、堅い場面で使う「私」のみが女性の自称詞となっている事実は、女性が常に礼儀正しく、かしこまって過ごす役割を与えられていることの象徴だといえる。
「実は江戸時代までは、身分によって話し方が異なることはあっても、すべての「日本人」が男女によって話し方や自称詞を使い分ける、という観念はありませんでした。性別による自称詞の使い分けや、男性らしい話し方、女性らしい話し方の区別が生まれたのは明治以降。近代化の流れの中で男女の言葉が非対称なものとなり、今日にいたっています」と金水教授。言葉が政治の意図、歴史の影響を受けて変わりうることは、Dialogueでもこちらの記事で言及したところだ。人の手によって作られてきたとも言える、日本語における男女の役割語の非対称性。同じく人の手によって、是正する方法はないのだろうか?
「タレントのあのちゃんや春風風花さんなど、近年、“ボク”という自称詞を使う女性が増えつつある。これは男女の役割語にバランスを取り戻そうとする自然治癒的な動きかもしれない、と思って観察を続けています」と金水教授。自分を“ボク”と呼んだり、自身の下の名前を自称詞として用いたり。女性が「私」「あたし」以外の自称詞の可能性を模索する傾向が自然発生的に起こっており、言葉におけるジェンダー・ギャップを埋める形で機能していることは非常に興味深い。「男性がくつろいでいる時、ありのままの自分を指し示す時に使える“俺”“僕”のような自称詞を女性が模索しているという現象は、注目すべき変化の兆候だと思います」と、金水教授もこの現状を前向きに分析している。
女性が自分を“ボク”と呼んだり、下の名前で呼んだりすることを、「女性らしくない」「子どもっぽい」と批判する風潮もあるだろう。しかし日本語が孕んでいるジェンダー・ギャップの問題を理解すれば、この現象をポジティブに捉えることもできるはず。そうやって自称詞における多様性を受け入れていくことは、日本社会に根付いた問題改善の一歩となるかもしれない。
表現の自由と、社会的倫理。
双方を大切に、揺れ動きながら前進していく。
「役割語がジェンダー・ギャップを助長しているかもしれない、という問題意識は広く持つべき。しかし役割語の非対称性や区別を全て無くすべきかというと、そうではないのが難しいところです」と金水教授は言う。役割語から性別や年齢といったバイアスをなくす方法は、実は意外と単純。全てのキャラクターが敬語で話せばいいのだという。しかし、全キャラクターが敬語で会話するアニメや漫画が、人々に愛されるだろうか?ストーリーや絵柄が同じでも、役割語が一切用いられていない作品の魅力は、大幅に損なわれてしまう可能性が高い。
また、キャラクターとのタッチポイントが多様化している現代においては、作り手だけでなく受け手のリテラシー向上も重要となる。「最近は、性区別を含んだ役割語に受け手が違和感を感じ、声をあげるシーンも増えてきている」と金水教授は話す。その一例として挙げられるのが、ビリー・アイリッシュのインタビュー記事について。該当の記事では、ビリーの発言が「〇〇だわ」「〇〇だと思うの」という、いわゆる女性的な役割語に翻訳されていた。ボディラインをあえて隠す中性的なファッションや、LGBTQの当事者であるという発言でも知られているビリーだからこそ、記事公開後に翻訳を疑問視する声が多発。日本語に訳される過程で本人が意図していないはずの「女性性」が付与されたことに、多くの人が批判的な声を上げた。Vogue JAPANは後にこの出来事を分析するコンテンツを作成しており、金水教授も対談に参加している3。
「こういった出来事を見ていると、役割語という概念に対する理解が少しずつ広がってきていること、作り手・受け手のリテラシーが徐々に育ってきていることを実感します。役割語を用いることでキャラクターを魅力的に見せられるという強み、一方で役割語を使うことで助長されてしまうジェンダー・ギャップなどの弱み。強みと弱みを柔軟にハンドリングして、多様性や揺らぎの中に価値を見出せるのが日本人の特性ですから、作り手と受け手が双方にリテラシーを高め合い、監視をし合う中でいつか適切なバランスを見つけていくことができると思います」と、金水教授はこれからのキャラクター文化を支える作り手・受け手の成長に期待を寄せる。
表現の自由や作品としての魅力をとるのか、キャラクターが社会に与える影響の広さを鑑みて倫理的な正しさを追求するのか。その関係性は多くの場合トレードオフとなるため、「これ!」という正解、正攻法はない。近年は、漫画家やアニメ制作会社といった専門的なクリエイターだけでなく、一般企業などもマーケティングやPRの一環としてキャラクターの力を借りる機会が増加している。だからこそこれからは、より多くの人にキャラクターが社会に与える影響を理解し、役割語の豊かさと問題点のバランスを検討し続ける姿勢が求められるようになるだろう。一見ハッピーなものにしか見えないキャラクターという概念を一歩深掘り、社会に良い影響を与える存在として発信していく。日本のキャラクタービジネスが世界に誇れる文化であり続けるために必要なマインドセットを、今回の金水教授のインタビューから深く学ぶことができた。
- 出典:経済産業省「エンタメ・クリエイティブ産業戦略 ~コンテンツ産業の海外売上高20兆円に向けた5ヵ年アクションプラン~」 ↩︎
- 出典:内閣府 男女共同参画局「男女共同参画に関する国際的な指数」 ↩︎
- Vogue JAPAN「「ことばとセクシュアリティ」をめぐる有識者会議──メディアに根付く役割語をアップデートせよ!」 ↩︎
interviewee: 大阪大学 金水 敏 名誉教授
Interview / Writing / Photo: Dialogue Staff
TOP IMAGE by Satoshi Kinsui, illustration from Yakuwarigo Karuta



